札幌の弁護士・会計士に遺産分割交渉・調停などの相続の相談をするなら

弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅3番出口直結 専用駐車場:無し)
公正証書遺言の基礎知識
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この中で、遺言者が自ら手書きして作成する自筆証書遺言と、公証人という公務員(ただし、国から給与はもらわず、公証人手数料令という政令で定められた手数料を受け取ります。)が作成する公正証書遺言が主に利用されています。今回は公正証書遺言について見ていきたいと思います。
【目次】
1.遺言とは
2.遺言の方式
3.公正証書遺言のメリット・デメリット
4.公正証書遺言を作成したいとき
遺言とは
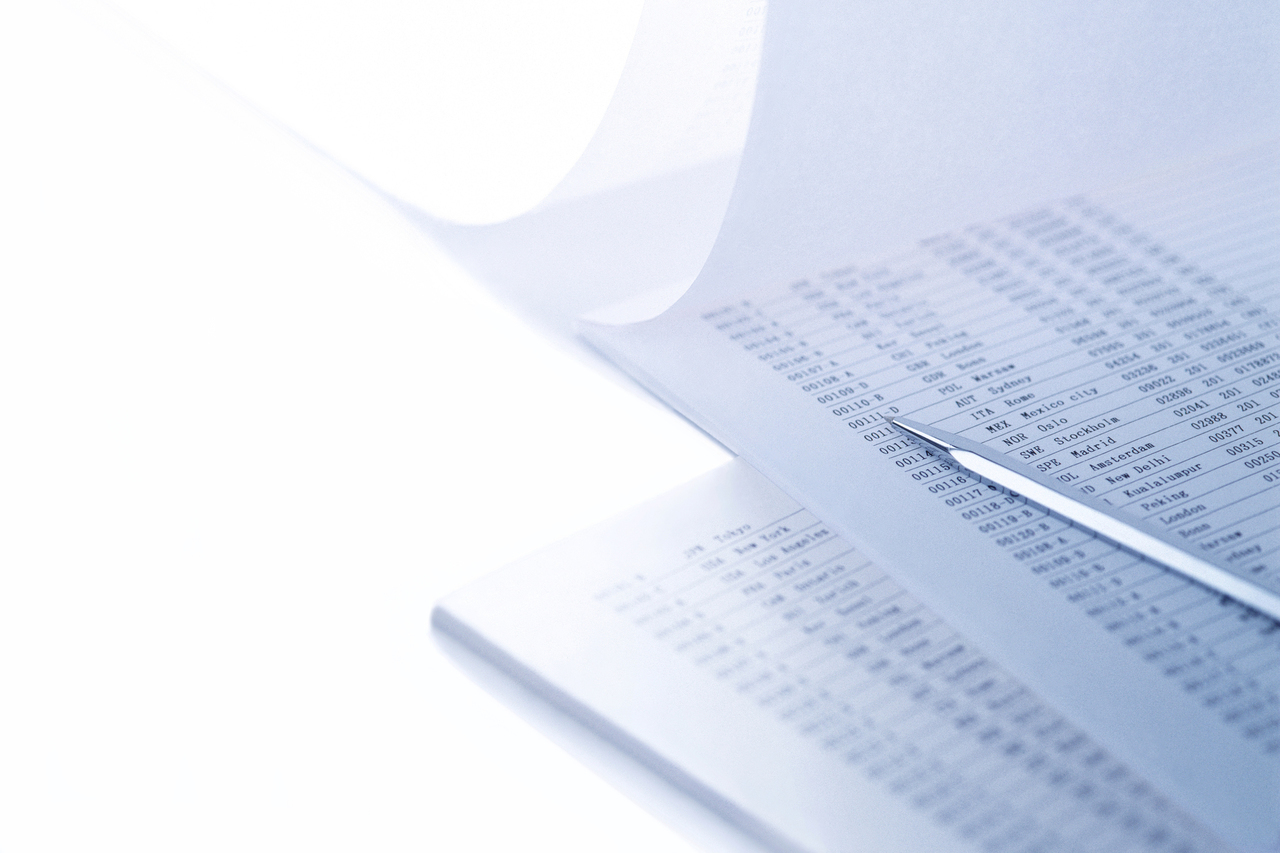
相続というと、民法に定めのある法定相続分が原則であるように考えている方が多いのですが、それは誤解です。
法定相続分の規定が適用されるのは、遺言による指定がない場合に限られます。民法は遺言者の意思を尊重するため、遺言による相続が最も優先され、次に法定相続分の定めという順番になるのです。
遺言の方式
遺言は、民法の定めるやり方(方式)で行わなければ無効になり、遺言としての効力が認められないことになります。
自筆証書遺言は遺言者一人で作成することが可能ですが、法律に従っていないと無効になってしまうので、注意しないと危険です。
公正証書遺言の場合は、法律に精通した公証人が作成に関与するため、無効となるリスクが低くなります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットとしては次のようながあります。
・先ほど述べたように無効となるリスクが低い
・遺言書の原本が公証役場で保管されるため、偽造、破棄、隠匿などの恐れがない
・相続開始後に裁判所で遺言書を確認する手続(検認)が不要
・相続開始後は相続人が公正証書遺言の検索システムにより、その存在を検索できる
公正証書遺言のデメリットとしては以下のような点が挙げられます。
・作成に手間や時間がかかる
・作成費用(手数料)がかかる
公正証書を作成したいとき
公正証書遺言を作成するには、公証役場に赴き、公証人に対して直接遺言を口頭で述べて(口授)作成してもらいます。
依頼する公証役場はどこでも構いません。私の事務所の近くだと、札幌中公証役場という公証役場があります。
行きやすさなど都合のよい公証役場を選んで、事前に連絡し、文案の作成や日程調整、必要書類の準備などを行います。通常は、遺産のリストを挙げ、不動産登記簿や、預貯金通帳の写しなどの資料が必要です(遺産の金額により手数料が変わってきます。)。
証人2名の立会いが必要になりますが、弁護士に依頼されるのであれば、弁護士や事務員が証人として立ち会うこともあります。
そのほかに、遺言者本人であることを証明するために、印鑑証明書などが必要になることがあります。
文案については、誰にどの遺産を承継させるかがメインの内容です。そのほかに、遺言の内容についての遺言者の考えを付言事項として残しておくこともあります。
このページを見た人がよく見るページ
封印された遺言の開封
外国人による遺言
自筆証書遺言の方式
財産の変動が見込まれる場合の遺言書の書き方
お気軽にお問合せください
新着情報・お知らせ
「借地人が死亡して相続人がいないとき」を更新しました。
「遺産に非上場株式がある時」を更新しました。
「祭祀承継者とはどのような人か」を更新しました。
こう法律会計事務所

住所
〒060-0042
北海道札幌市
中央区大通西10丁目4
南大通ビル2F
アクセス
札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅3番出口直結
専用駐車場:無し
受付時間
9:30~18:30
定休日
土曜・日曜・休日


